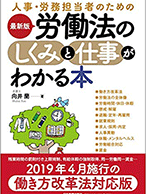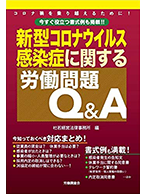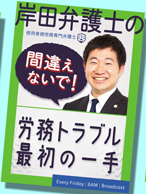- 03-6275-0691 受付時間:平日9:00~17:00
-
日本全国に対応しております!
-
受付時間:平日9:00~17:00
-
日本全国に対応しております!
日本全国に対応しております!
受付時間:平日9:00~17:00
日本全国に対応しております!
更新担当者 弁護士 樋口陽亮 (ひぐち ようすけ)

目次
労働審判は、労働争議において迅速かつ適正な解決を目指すための制度です。そのため、労働審判によって下される裁定は、一定の法的効力を有しており、当事者間の紛争解決に大きな役割を果たします。
特に、労働審判の主文には、判決と同様の効力が認められていますので、労働者側と使用者側の双方がこれに従う必要があります。このように、労働審判の決定は、実際の労働関係に対して非常に大きな影響を与える可能性があるため、当事者はその内容をしっかりと把握しておくことが重要です。
一方で、労働審判に不服がある場合、労働者や使用者は異議申立てをすることができます。この異議申立ては、審判書の送達または告知を受けてから2週間以内に行う必要があり、所定の手続きを遵守することが求められます。
異議申立てを行うことで、労働審判の効力は失われ、この後には新たに訴訟が提起されることになりますので、慎重に検討する必要があります。
労働審判を通じた労働問題の解決は、企業にとっても重要な課題であり、適切な法的アドバイスを受けることで、迅速かつ円滑に問題を解決することが可能です。
前項で申立のうち2割が労働審判を言い渡されて終わると述べました。
しかし、審判を言い渡されても、異議申し立てを行うことはできます。
現状では、労働審判を言い渡されたうちの6割が異議を申し立てを行っています。
当事者のうちどちらか又は両方が労働審判に対し異議申し立てを行えば、労働審判は効力を失います。
しかし、異議申し立てがなされれば、労働審判は全く意味がなくなるのか、というとそうではありません。
法的には労働審判が失効したとしても、労働審判書を異議申し立て後の訴訟で証拠として提出することが出来ます。
労働審判委員会は、相当長い時間をかけて直接当事者から話を聞いて労働審判の結果を出しますので、異議申し立て後の訴訟においても、後に担当した裁判官は労働審判結果を重く受け止めます。
(もちろん事案によりますので、一概にはいえませんが)私の実務上の感覚では、特に新しい証拠を異議申し立て後に提出できないと、労働審判と同じ結論が出ることが多いように思えます。
むしろ時間と弁護士費用がかかっていますので、労働審判時の和解金額よりも、さらに加算した金額を通常訴訟移行後の和解で支払うこともあります。
ですから、労働審判への対応は極めて重要と言えます。
ここでは、異議申立てを行う際の判断基準を解説します。
訴訟に移行することで結論が有利に変更される可能性があるかどうかが重要です。
また、訴訟に移行した場合にかかる期間や費用も考慮する必要があります。
これらの要素を総合的に検討し、最適な選択をすることが大切です。
労働審判は、原則として3回の期日内で迅速に審判が下されますが、訴訟の場合はその期日や期間に上限がなく、互いの主張が尽きるまで続きます。
そのため、労働訴訟にかかる期間は通常6ヶ月から1年程度になることが多く、場合によってはそれ以上かかることもあります。
異議を申し立てるにあたっては、この長期化の可能性も十分に検討する必要があります。
どのようにして弁護士と共に、労働審判に際して生じるトラブルを解決するのかのご参考にしてください。
また、労働問題で起きる代表的なトラブルや弁護士に相談すべき理由について解説した記事もございますので、ぜひご一読ください。
例えば、セクハラ等を行った従業員に配転命令を出したところ、該当従業員が組合に加入し、パワーハラスメントであると主張して団体交渉を要求してきたケースがありました。
このケースでは、パワーハラスメントでないことを立証し、解決に導くことができました。
また、営業回りの従業員から残業代請求の訴訟が提起された事例もございます。
この際、請求額の約1割の金額で和解による解決を図ることができました。
このような具体例に基づいた解決事例を通じて、労働審判の効果や重要性を理解していただければ幸いです。
どのようなトラブルについても、早期に適切なアドバイスを受けることで、より良い解決策に繋がる可能性があります。
使用者側の労務トラブルに取り組んで40年以上。700社以上の顧問先を持ち、数多くの解決実績を持つ法律事務所です。労務問題に関する講演は年間150件を超え、問題社員対応、残業代請求、団体交渉、労働組合対策、ハラスメントなど企業の労務問題に広く対応しております。
まずはお気軽にお電話やメールでご相談ください。
お電話・メールで
ご相談お待ちしております。
受付時間:平日9:00~17:00
受付時間:平日9:00~17:00
日本全国に対応しております!
この記事の監修者:向井蘭弁護士

杜若経営法律事務所 弁護士
弁護士 向井蘭(むかい らん)
【プロフィール】
弁護士。
1997年東北大学法学部卒業、2003年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。
同年、狩野祐光法律事務所(現杜若経営法律事務所)に入所。
経営法曹会議会員。
労働法務を専門とし使用者側の労働事件を主に取り扱う事務所に所属。
これまで、過労死訴訟、解雇訴訟、石綿じん肺訴訟。賃金削減(就業規則不利益変更無効)事件、男女差別訴訟、団体交渉拒否・不誠実団体交渉救済申立事件、昇格差別事件(組合間差別)など、主に労働組合対応が必要とされる労働事件に関与。近年、企業法務担当者向けの労働問題に関するセミナー講師を務める他、労働関連誌への執筆も多数
労働審判の関連記事
キーワードから記事を探す
労務対策コラムの新着記事
当事務所は会社側の労務問題について、執筆活動、Podcast、YouTubeやニュースレターなど積極的に情報発信しております。
執筆のご依頼や執筆一覧は執筆についてをご覧ください。