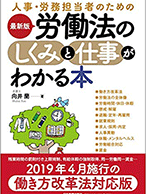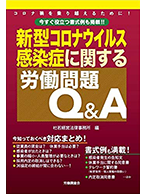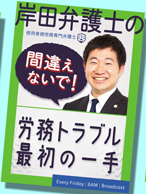- 03-6275-0691 受付時間:平日9:00~17:00
-
日本全国に対応しております!
-
受付時間:平日9:00~17:00
-
日本全国に対応しております!
日本全国に対応しております!
受付時間:平日9:00~17:00
日本全国に対応しております!
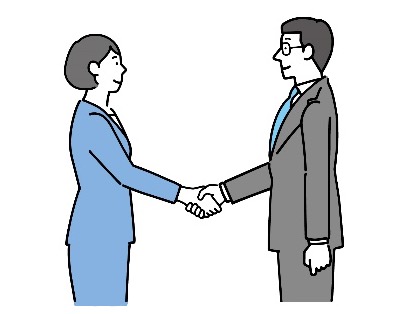
企業は、労働組合との間でユニオンショップ協定を締結している、あるいは労働組合から締結することを求められることがあります。
本ページでは、弁護士が「ユニオンショップ協定とはなにか」「企業はユニオンショップ協定を結ぶ義務があるのか」など、企業がユニオンショップに関して、最低限理解しておくべきことを解説いたします。
目次
ユニオン・ショップ協定とは、労働組合が使用者に対し、雇い入れられた労働者のうち、当該労働組合に加入しない者及び当該労働組合から脱退しもしくは除名された者の解雇を義務づける労働組合と使用者との取り決めのことです。ユ・シ協定と呼ばれることもあります。
また、ユニオン・ショップ協定を締結する労働組合は、「特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する労働組合(労組法上の労働組合)」(労働組合法7条1項ただし書)という要件を充たしていなければ効力を有しないと解されています。
ちなみに、平成23年の厚生労働省の調査によると、組合員数30人以上の労働組合の6割以上がユニオン・ショップ協定を締結しているとされています。
では、使用者には労働組合とユニオン・ショップ協定を結ぶ義務はあるのでしょうか。
労働組合にとっては、ユニオン・ショップ協定を締結すれば団体交渉でより強い圧力を行使したり、財産的基盤を充実させたりすることができるため、使用者に対してユニオン・ショップの締結を求める場合があります。
しかし、ユニオン・ショップ協定は、契約と同様、使用者と労働組合の合意によって締結されるものです。したがって、使用者にはユニオン・ショップ協定を結ぶ義務はなく、締結を拒否しても問題はありません。
もっとも、使用者にとっても、労働組合とユニオン・ショップ協定を結ぶことにはメリットがあります。労働組合の組織力・統制力が高まれば、36協定の締結、人事制度の改定などはすべて労働組合を通して協議し解決していくことができるので、従業員個人から同意をもらったり、説明を行ったりする必要がなくなります。使用者にとっては窓口が一本化されていれば労使交渉がしやすいです。
以上の点を踏まえて、使用者は労働組合とユニオン・ショップ協定を結ぶか否かを判断することになります。
ユニオン・ショップ協定の中には、使用者がユニオン・ショップ協定に基づいて解雇するか否か決定権を有するものがあったり、様々なものがあります。
【文例1】
「会社は、労働組合より除名された者、労働組合に加入しない者、労働組合から脱退した者を1ヶ月以内に解雇しなければならない。」
※これは労働組合に加入しない者、脱退した者、除名された者全てを使用者が解雇しなければならないと定めた例です。
【文例2】
「会社は、従業員であって労働組合より除名された者は解雇する」
※これは、労働組合に加入しない者、脱退者については解雇義務を定めず、労働組合から除名された者のみを解雇義務の対象とする例です。
【文例3】
「会社は、労働組合より除名された者、労働組合に加入しない者、労働組合から脱退した者を原則として解雇する。ただし、解雇について異議がある場合は、会社と労働組合は協議して決定する。」
※これは、使用者が必ず労働組合に加入しない者、脱退した者、除名された者を解雇すると定めず、原則として解雇すると定め、使用者に裁量をもたせた例です。尻抜けユニオンといいます。
【文例4】
「会社の従業員はすべてA労働組合の組合員でなければならない」
※これは、従業員の労働組合加入義務を定めるものの、解雇義務を敢えて規定しない例です。宣言ユニオンといいます。
ユニオン・ショップ協定にもとづく解雇は、従業員の退職という重大な効果をもたらします。そのため、使用者がユニオン・ショップ協定にもとづく解雇を行わない余地を残す場合が多く見られます。
使用者は、労働組合とユニオン・ショップ協定を結ぶとしても、会社と労働組合の関係、会社の社風、会社の規模を考慮して、上記文例1から4のようにユニオン・ショップ協定の文言については慎重に検討する必要があります。
では、使用者が労働組合と、労働組合を脱退した者を全て解雇するとのユニオン・ショップ協定を結んだとして、労働組合員が脱退後に他の労働組合に加入した場合もユニオン・ショップ協定に基づく解雇は有効なのでしょうか。
ユニオン・ショップ協定は、解雇の威嚇により労働者を特定の労働組合に加入することを事実上強制するものであるため、どの労働組合に加入するか選択する自由(積極的団結権)や労働組合に加入しない自由(消極的団結権)との関係で、ユニオン・ショップ協定が違法、無効であると考える学説もありますが。
もっとも、判例(三井倉庫港運事件判決、最一小判平元・12・14民集43巻12号2051頁/労判552号6頁)は、会社と労働組合がユニオン・ショップ協定を結んでいたにもかかわらず、労働組合を脱退し、その直後他の労働組合に加入した従業員を、その後会社がユニオン・ショップ協定にもとづいて解雇した事案について、以下のように述べています。
「労働者には、自らの団結権を行使するため労働組合を選択する自由があり、また、ユニオン・ショップ協定を締結している労働組合(以下「締結組合」という。)の団結権と同様、同協定を締結していない他の労働組合の団結権も等しく尊重されるべきであるから、ユニオン・ショップ協定によって、労働者に対し、解雇の威嚇の下に特定の労働組合への加入を強制することは、それが労働者の組合選択の自由及び他の労働組合の団結権を侵害する場合には許されないものというべきである。
したがって、ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが、他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、右の観点からして、民法90条の規定により、これを無効と解すべきである(憲法28条参照)。
そうすると、使用者が、ユニオン・ショップ協定に基づき、このような労働者に対してした解雇は、同協定に基づく解雇義務が生じていないのにされたものであるから、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当なものとして是認することはできず、他の解雇の合理性を裏付ける特段の事由がない限り、解雇権の濫用として無効であるといわざるを得ない。」
つまり、上記判例は、ユニオンショップ協定は、従業員の他の労働組合を選択する自由を制約するものですから、従業員がユニオンショップ協定を結んでいる労働組合を脱退して、他の労働組合に加入した場合は、たとえユニオンショップ協定に定めがあっても解雇をすることは許されないと判断しています。したがって、ユニオンショップ協定を結んでいても、従業員が労働組合を脱退して他の労働組合に加入した場合は、解雇することはできません。
また、社内に複数の労働組合があり、そのうちの一つが会社とユニオンショップ協定を結んでいるが、従業員がユニオンショップ協定を締結していない労働組合に加入した場合も、解雇することはできません。従業員の労働組合を選択する自由を保障する必要があるからです。
A1 厚生労働省の行政解釈上、締結時には過半数を代表していて、その後に過半数を失った場合は、協定は失効すると解されています。
A2 使用者がユニオン・ショップ協定に基づいて解雇義務を負うのは、労働者が有効な脱退・除名により組合員資格を喪失した場合に限られます。
判例上も、除名が無効である場合には、使用者はユニオン・ショップ協定に基づく解雇義務を負わず、他に解雇の客観的合理性及び社会通念上の相当性を基礎付ける特段の事情がない限り、解雇は権利濫用として無効となると解されています(日本食塩製造事件・最二小判昭和50・4・25民集29巻4号456頁)。
したがって、貴社としては除名が無効とされるリスクを負うことになります。
団体交渉の解決事例として、当事務所では以下のようなものがございます。どのようにして弁護士と共に、団体交渉に際して生じるトラブルを解決するのかのご参考にしてください。
また、労働問題で起きる代表的なトラブルや弁護士に相談すべき理由について解説した記事もございますので、ぜひご一読ください。
ユニオンショップ協定は、企業へのメリットもあります。
しかし、その内容を十分に理解しないまま、協定を結んでしまった場合、上記例にも記載の通り解雇に関するトラブルが生じ、裁判にまで発展してしまう可能性もあります。
ユニオンショップ協定を結ぶか悩んでいる場合は、一度、弁護士に相談することをおすすめします。
杜若経営法律事務所は、使用者側の労務トラブルに取り組んで40年以上。700社以上の顧問先を持ち、数多くの解決実績を持つ法律事務所です。労務問題に関する講演は年間150件を超え、問題社員対応、残業代請求、団体交渉、労働組合対策、ハラスメントなど企業の労務問題に広く対応しております。
団体交渉についても、当事務所は社労士の先生からのご紹介によるご依頼も多数引き受けており、社労士の先生方が手に負えないようなハードな組合問題も多数経験しております。
まずはお気軽にお電話やメールでご相談ください。
|
団体交渉 |
月10万×3ヵ月 から |
|
日当 |
弁護士人数によらず、10万円/回 |
お電話でのメールでの
ご相談・ご予約をお待ちしております。
受付時間:平日9:00~17:00
受付時間:平日9:00~17:00
日本全国に対応しております!
この記事の監修者:向井蘭弁護士

杜若経営法律事務所 弁護士
弁護士 向井蘭(むかい らん)
【プロフィール】
弁護士。
1997年東北大学法学部卒業、2003年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。
同年、狩野祐光法律事務所(現杜若経営法律事務所)に入所。
経営法曹会議会員。
労働法務を専門とし使用者側の労働事件を主に取り扱う事務所に所属。
これまで、過労死訴訟、解雇訴訟、石綿じん肺訴訟。賃金削減(就業規則不利益変更無効)事件、男女差別訴訟、団体交渉拒否・不誠実団体交渉救済申立事件、昇格差別事件(組合間差別)など、主に労働組合対応が必要とされる労働事件に関与。近年、企業法務担当者向けの労働問題に関するセミナー講師を務める他、労働関連誌への執筆も多数
団体交渉・労働組合対策の関連記事
キーワードから記事を探す
労務対策コラムの新着記事
当事務所は会社側の労務問題について、執筆活動、Podcast、YouTubeやニュースレターなど積極的に情報発信しております。
執筆のご依頼や執筆一覧は執筆についてをご覧ください。