- 03-6275-0691 受付時間:平日9:00~17:00
-
日本全国に対応しております!
-
受付時間:平日9:00~17:00
-
日本全国に対応しております!
日本全国に対応しております!
受付時間:平日9:00~17:00
日本全国に対応しております!
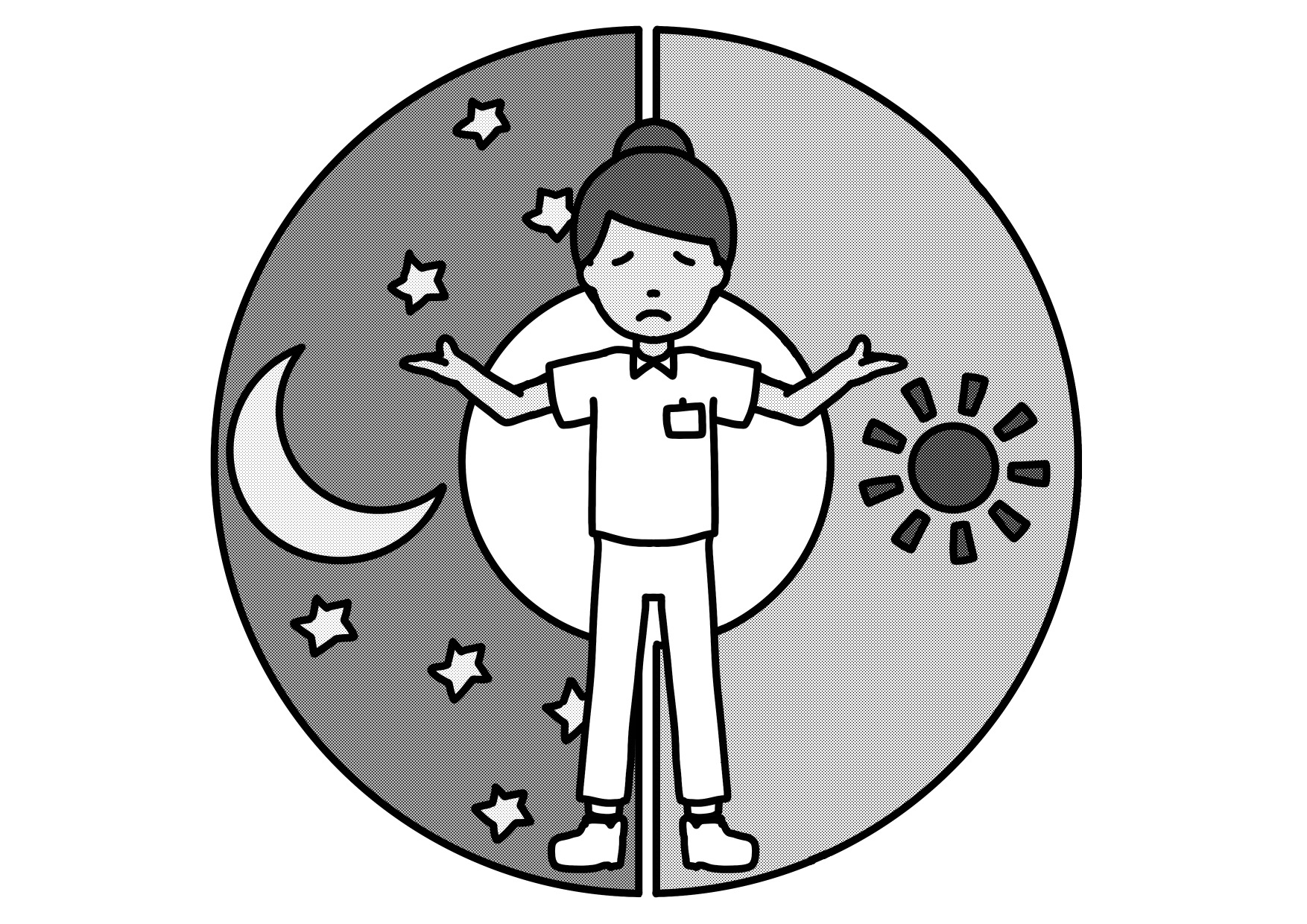
お電話・メールで
ご相談お待ちしております。
受付時間:平日9:00~17:00
受付時間:平日9:00~17:00
日本全国に対応しております!
目次
一部の職種の夜勤では、夜勤手当を支払う代わりに仮眠を取っている時間等に対して賃金を支払わないことがあります。その趣旨は「労働時間とは認めないけど、何かあった時に対応してもらうから夜勤手当を支払う」ということだと思います。何とも曖昧な夜勤手当の位置づけです。
仮眠時間が労働時間であると認定された場合、果たしてこの夜勤手当は基本給と同じような割増賃金の算定基礎となるのか、夜勤手当が割増賃金の算定基礎になるのか、言い換えれば夜勤の時給単価を日中勤務時間帯と別単価とすることができるのかについて明確に判断した裁判例は私の知る限りありませんでした。この点について、社会福祉法人A事件控訴審(東京高裁令和6年7月4日判決)が出ましたのでご紹介します。
社会福祉法人である一審被告のグループホームにおいて、生活支援員として午後9時から翌朝6時までの夜間時間帯に勤務していた一審原告の同時間帯の割増賃金の算定基礎について、いわゆる一般的な基本給が単価になるのか、泊まり勤務に対して支払われている夜勤手当等が単価になるかが争点になった事案の控訴審になります。一審判決(社会福祉法人A事件・千葉地裁令和5年6月9日判決)では夜勤時間帯に支払われている手当等が割増賃金の算定基礎になると判断されました。
一審判決については弊所岸田弁護士がニュースレターで解説しました(https://x.gd/tcFwf)。
今回はその控訴審をご紹介したいと思います。
その上で、「労働契約において、夜勤時間帯について日中の勤務時間帯とは異なる時間給の定めを置くことは、一般的に許されないものではないが、そのような合意は趣旨及び内容が明確となる形でされるべきであり、本件の事実関係の下で、そのような合意があったとの推認ないし評価をすることはできず、法人の上記主張は採用することができない。」と判断しました。
要するに、法人は夜勤時間帯についてはそもそも労働時間として認識していなかったのだから、1回に付き6000円の夜勤手当が夜勤時間帯の労働に対する対価には当たらないと判断しました。
一審では、裁判所が夜勤勤務時間帯の時給単価を6000円÷8時間=750円として計算していたため、最低賃金すら割っていたことから話題になりましたが、二審では6000円は基本給と同じ位置づけとなり、その前提で割増賃金が計算されることになりました。
今回の判決は以下の通り判断しました。なかなかありそうで無い判決で今後の実務に影響を与える可能性があります。
従来から、一定の時間帯の労働時間を他の時間帯の労働時間と異なる時給単価で契約をすることは可能か?という論点がありました。使用者としては、特に労働密度の低い手待ち時間や待機時間などの場合に別時給単価を支払いたいと考えますが、今回明確に裁判所は、別の時給単価で契約することは可能である旨判断しました。
今回、一審と異なり、二審で法人側がなぜ敗訴したかというと、そもそも夜勤時間帯を労働時間と認識せず運用していたのだから、夜勤手当をそのまま夜勤時間帯に対する賃金と扱うことはできないと判断したためです。裏返して言うと、夜勤時間帯を労働時間と認め、その対価としての時給であることを明確に合意すれば(採用時の賃金規則に定めてあれば可能です)、夜勤手当をそのまま夜勤時間帯に対する賃金と扱うことができます。
この裁判例において法人側代理人を担当した戸田哲弁護士のHP(https://x.gd/2q4b2)に以下の文献が引用されておりました。私も知りませんでしたが、最低賃金以下の時給単価をある時間帯に限って設定して合意をすることは違法になるとは限らないとのことです。そうなると、労働密度が低い時間帯について時給を最低賃金以下に設定することも可能となります。もっとも、賃金総額は最低賃金額を上回る必要はあります。
「労働契約において、時間ごとに異なる賃金を定めた場合、特定の時間について最低賃金を下回っているとしても、賃金支払日に支払われた賃金の総額が最低賃金額を上回っている場合には、4条1項違反の問題は生じない。 最低賃金額の表示期間単位が時間に一本化されているのはあくまで表示上のものであり、賃金をどのように決定するかは契約自由の範疇である。そのため、労基法上の労働時間の一部について最低賃金を下回る合意がなされたとしても、直ちに最低賃金法4条1項違反の問題は生じない。」引用元:有斐閣コンメンタール「注釈労働基準法・労働契約法 第1巻」365頁以下
「最低賃金法の規制も、すべての労働時間に時間当たりの最低賃金額以上の賃金を支払うことを義務付けるものではない。」引用元:荒木尚志「労働法(第5版)」209頁
今回の判決をもとにすれば、以下の場面で特定の時間帯の時給単価を低めに設定することが可能になります。実際の実働時間は短いわけですから、一時間当たりの時給を下げて雇用契約書に明記することが可能になります。労働時間に当たるかをあいまいにして、手当のみを支払うよりは法的リスクは下がります。検討に値するとは思います。
(1) 医師や看護師のオンコール勤務の時給単価
(2) 運送会社における手待ち・待機時間帯の時給単価の設定
(3) 警備会社における仮眠時間帯の時給単価の設定
この記事の監修者:向井蘭弁護士

杜若経営法律事務所 弁護士
弁護士 向井蘭(むかい らん)
【プロフィール】
弁護士。
1997年東北大学法学部卒業、2003年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。
同年、狩野祐光法律事務所(現杜若経営法律事務所)に入所。
経営法曹会議会員。
労働法務を専門とし使用者側の労働事件を主に取り扱う事務所に所属。
これまで、過労死訴訟、解雇訴訟、石綿じん肺訴訟。賃金削減(就業規則不利益変更無効)事件、男女差別訴訟、団体交渉拒否・不誠実団体交渉救済申立事件、昇格差別事件(組合間差別)など、主に労働組合対応が必要とされる労働事件に関与。近年、企業法務担当者向けの労働問題に関するセミナー講師を務める他、労働関連誌への執筆も多数
その他の関連記事
当事務所は会社側の労務問題について、執筆活動、Podcast、YouTubeやニュースレターなど積極的に情報発信しております。
執筆のご依頼や執筆一覧は執筆についてをご覧ください。